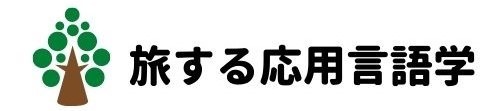Michael Long
フォーカス・オン・フォーム(Focus on Form)は、1980年代後半~1991年にMichael H Longが提唱した概念です。
- Long, M. (1991). Focus on Form: A Design Feature in Language Teaching Methodology. In K. De Bot, R. Ginsberg, & C. Kramsch (Eds.), Foreign Language Research in Cross-Cultural Perspectives (pp. 39-52). Amsterdam: John Benjamins.
↑これはLongのFonFの初期の論文の一つです。
なお、フォーカス・オン・フォームはよくFonFと略されます。この記事でも以後、FonFを使います。
LongはFonFを以下の2つと区別しています。
- フォーカス・オン・フォームズ(Focus on Forms(FonFs))
- フォーカス・オン・ミーニング(Focus on Meaning(FonM))
今回は、まず上記の2つを説明し、その後本題であるFonFについて紹介します。
フォーカス・オン・フォームズ(Focus on Forms(FonFs))
FonFsとは
まず、フォーカス・オン・フォームズ(Focus on Forms (FonFs))です。
フォームに「s」がついていることからわかる通り、複数の言語形式に着目する指導法です。よくFonFsと略されます。
FonFsでは、文法や文型を中心に組み立てられた構造シラバスに基づき、文法・語彙を中心に学びます。
文法訳読法やオーディオリンガルメソッドなどがFonFsの例としてよく挙げられます。
FonFsの問題
FonFsの問題として、文法を習ったところで使えない、ということがあげられます。
また、正確さがあっても流暢さがないという問題も指摘されています。
フォーカス・オン・ミーニング(Focus on Meaning(FonM))
FonMとは
フォーカス・オン・ミーニング(Focus on Meaning (FonM))は、意味を重視しています。
これは、FonFsの逆で、言語形式(文法や語彙)は気にせず、コミュニケーション(意味のやり取り)を重視するものです。
幼児が母語を学ぶのと同じような形で第二言語を学ぶナチュラルアプローチや、第二言語で教科を学ぶイマージョンプログラムなどがFonMの例としてあげられます。
FonMの問題
問題としては、流暢にはなりますが、正確さが身に着かないという問題があります。
ただ、目標言語を聞いて、話しているだけでは、間違いが化石化(間違いが固定してしまうこと)するなど、一部の文法項目が定着しないままになることもあります。
フォーカス・オン・フォーム(Focus on Form(FonF))とは?
FonFとは
そして、本題のフォーカス・オン・フォーム(FonF)ですが、これは上記に述べたFonFsとFonMの欠点を補うような指導法と考えられます。
Long(1991)は以下のようにいっています。
overtly draws students’ attention to linguistic elements as they arise incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning or communication (p. 45-46)
クラスの焦点が意味やコミュニケーションであるときに、必要に応じてあえて言語形式にも学生の注意をむけさせること
基本はコミュニケーション活動を中心とした活動を中心とするのですが、必要に応じて言語形式にも注意を向けさせるということです。
その例としては、学習者の誤用を言い直すこと(リキャスト)などがあげられています。
当初はLongは、この言語形式に着目させるときは、短時間で暗示的に示す(つまり、いい間違いを言い直す程度で、文法などの説明はしない)ことを提唱していました。また、計画的というより、必要に応じて随時行うというスタンスだったようです。
ただ、その後、FonFの研究が発展するに従い、計画的FonFというような、教員が事前準備しておくようなものや、明示的に文法説明を行うようなものも含められるようになっています。
FonFの発展
FonFは、当初は従来の指導法に対する、新たな指導法として提唱されました。
ただ、その後は、指導法にとどまらず、言語形式・意味・機能を同時に処理するための言語処理モードとしても考えられるようになります。
さらに、指導法としても、FonFを実現するような教授法として、1990年代初頭からTask-based Language Teaching(タスクベースの教授法)も提唱されています。
興味のある方は
- Doughty, Catherine, and Jessica Williams. Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. The Cambridge Applied Linguistics Series. Cambridge University Press. 1998.
1998年なので古いですが、FonFについてまとめてある教科書的な本です。
日本語では英語教育でFonFについての書籍がいくつか出版されているようです。
- 和泉伸一. フォーカス・オン・フォームと CLIL の英語授業: 生徒の主体性を伸ばす授業の提案. Vol. 5. アルク, 2016.