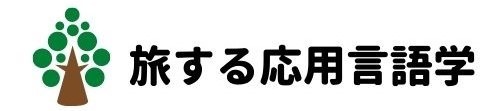「自己」という視点を取り入れたモチベーション研究
2000年代になると、学習者の「自己」に着目した研究が増えます。
DörnyeiとUshiodaは、以下の本で「自己」という視点からモチベーションを考える必要があるといっています。
- Dörnyei, Zoltán, and Ema Ushioda, eds. Motivation, language identity and the L2 self. Vol. 36. Multilingual Matters, 2009.
この本の中で、Dörnyeiは、心理学の理論を踏まえた「自己」という概念を取り入れた「L2 Motivation Self System(第二言語における動機づけ自己システム」を紹介しています。
- Dörnyei, Zoltán. The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Routledge, 2005.
↑ちなみにこの「L2 Motivation Self System」は2005年に出版されたこの本にも紹介されています。
今回はこのL2 Motivation Self Systemについて紹介します。
L2 Motivation Self System
L2 Motivation Self Systemでは、以下の3つの概念を使って、モチベーションを説明しています。
- L2理想自己(Ideal L2 Self)
- L2義務自己(Ought-to L2 Self)
- L2 学習経験(L2 learning experience)
この理論は、心理学の「possible selves theory(可能自己理論 (Markus & Nurius, 1986)」や「self-discrepancy theory(自己不一致理論)(Higgins, 1987)」を取り入れたものです。
L2理想自己
L2理想自己とは、第二言語(L2)を使って、将来どういった自分になりたいかという理想の自己像です。
将来、英語を使って本を書きたいと考えた場合、その理想の自己と現在の自分との差を埋めることが学習の動機となります。
L2義務自己
L2理想自己が自分の描く理想の自己像だったのに対し、L2義務自己は、他者が自分に期待している自己、ならなければいけない自己のことです。
家族・上司・同僚に認められたいからという承認欲求から学習に取り組む場合などがそれが当たります。
「悪い学生と思われたくない」「できない部下と思われたくない」など、マイナスの影響を避けるために、第二言語学習に取り組むことが多くなります。
L2学習経験
「L2理想自己」と「L2義務自己」は自己像のことでしたが、「L2学習経験」はその時々の学習・環境における動機づけのことです。
例えば、授業が楽しかったり、クラスメートの関係が良好だったりすると、学習は促進されると考えられます。
また、学習経験を通して新たに自分の得意なことに気づき、それが学習動機につながることもあると思います。
まとめ
2000年代からのモチベーション研究は、この「自己」という概念を取り入れたものが多いようです。また研究成果を教育に応用する研究も多くされています。
なお、最近はDirected Motivational Currentsという理論も提唱されています(Muir and Dörnyei 2013)。
- Dörnyei, Zoltán, Alastair Henry, and Christine Muir. Motivational currents in language learning: Frameworks for focused interventions. Routledge, 2015.
↑この本にも説明されています。
「Current」というのは「(水の)流れ」という意味もありますが、例えば川の流れは雨が降ると勢いを増したり、障害物があると蛇行したりと予測不可能なことが多々あります。動機も同じく予測不可能で、ふとした要因でやる気が上がったり、下がったりします。こういった予測不可能性も取り入れた理論です。
また「Directed(方向性をもった)」とありますが、明確なビジョンがないと、強い学習の動機づけにはつながりません。多少、時にやる気が落ちたときでも、長期的なビジョンがあれば、一定の方向性に向かって進むことができます。こういう長期的な展望も捉えた理論のようです。
詳しくはこちらもご覧ください。
モチベーション研究の変遷に関する記事
- モチベーション研究の変遷①:道具的動機付け・統合的動機付け
- モチベーション研究の変遷②:Deci とRyanの自己決定理論
- モチベーション研究の変遷③:Dörnyeiのプロセス重視のモチベーションモデル
- モチベーション研究の変遷④:DörnyeiのL2 Motivational Self System