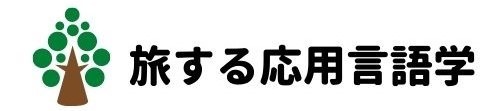Cookはハワイ大学マノア校の教授で、スピーチスタイル(丁寧体(~です/ます)、普通体(「~だ」などの「~です/ます」でない形)の研究などしています。
- Cook, Haruko Minegishi (2001) Why Can’t Learners of Japanese as a Foreign Language Distinguish Polite from Impolite Speech Styles? In Kenneth R. Rose and Gabriele Kasper (Eds.) Pragmatics in Language Teaching.
スピーチスタイルにはあまり注意がいかない
この論文では、大学2年生レベルの日本語クラスを履修する学生120人に、3人の就職面接での自己紹介のオーディオテープを聞かせたらしいのです。この3人のうち1人は日本語は流暢なのですが、カジュアルに話していて、また、「私は日本語はとてもよくできますよ」などという直接的な表現も使っており、教師から見ると全くもって就職面接では不適切な人物だったのですが、学生の約80%がその人が最もふさわしいと選んだそうです。
学生は、就職面接で話された「内容」には注目していたのですが、話し方などの語用論的な側面には注意が向いていなかったといっていました。
スピーチスタイルに注意がいかない原因
この原因の一つとしては、教師は「丁寧体」(です/ます)と「普通体」(カジュアルな言葉)の違いは教えていたのですが、それ以外の語用論的特徴(自分の能力について謙遜して話すことや、「どうぞよろしくお願いします」のような定型表現、終助詞「よ」等)は教師本人が明示的に意識しておらず、学生にも伝わっていなかったことがあると言っていました。
この論文でも書いていましたが、スピーチスタイルの適切さを判断するためには、ただ丁寧体と普通体の違いを知るだけでは不十分な場合が多く、その他の語用論的特徴や文化的規範も知る必要があると思います。
ただ、教師側も気づかないような特徴をどう教えていくのかというのは難しい課題だなと思いました。