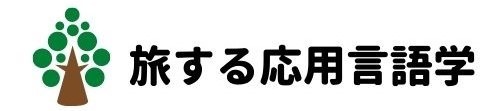この記事では、「トランスランゲージング(translanguaging)」という用語について説明します。
まず、translanguagingの用語とその由来を見た後に、バイリンガリズムとの違いも紹介します。
トランスランゲージング(Translanguaging)とは
Translanguagingとは
Translanguagingとは、バイリンガル・マルチリンガルの人が、フレキシブルに複数のことばを使う言語実践を指します。
Translanguagingの例として、作家の温又柔のお母さんの話し方があげられます。
温又柔は台湾で生まれ、3歳の時に東京に移り住み、台湾語・中国語・日本語の中で育った作家です。
彼女のエッセイ『台湾生まれ 日本語育ち』で、彼女のお母さんの会話が紹介されています。
ティアー・リン・レ・講話、キリクァラキリクァラ、ママ、食べられないお菓子。
(あんたたちがペチャクチャしゃべっているのを聞いていると、お菓子を食べそびれちゃう) (p. 33)
彼女のお母さんは、日本語・中国語・台湾語を「奔放に繋ぎあわせ」て話していたそうです。
これは一例ですが、バイリンガル・マルチリンガル同士の会話だと、いわゆる「日本語」「英語」といった言語の境界を気にすることなく、柔軟に言語がつなぎ合わされることが多いです。
このようなバイリンガル・マルチリンガルの言語実践をTranslanguagingといいます。
また、Translanguagingはバイリンガル・マルチリンガル教育と密接に関連しており、その言語実践を活用した教育的アプローチを指す場合もあります。
由来
もともとはウェールズの教育者であるCen Williams (1994)が作った、ウェールズ語のtrawsieithuに由来します。
Williamsは、ウェールズ語・英語のバイリンガル教育で、英語で読んだ内容についてウェールズ語で書いたり、ウェールズ語で聞いたことを英語で書いたりと、インプットとアウトプットの言語を意識的に変える教育法を提唱しました。
Baker (2001)がこのtrawsieithuを英語に翻訳し、translanguagingとして広く使われるようになりました。
バイリンガリズム・相互依存モデル・トランスランゲージングの違い
Translanguagingは、二言語併用を指すコードスイッチングという用語とはどう違うのでしょうか。
結論からいうと、translanguagingの特徴は、今までの用語と言語に対する考え方が違います。
(※といいつつ、translanguagingの定義は時代によって変化しているため、あくまで以下の説明はGarcía and Li(2014)『Translanguaging: Language, Bilingualism and Education』を基にしたものです。)
今までの言語に対する考え方をまとめると、以下の図のようになります(Garcia and Li 2014, p.14をもとに作成)。
下記の図のLというのは「言語体系」(「日本語」「英語」「中国語」などのいわゆる「言語」のことです)、F1というのは「言語特徴」(各言語内の語彙など)のことです。
バイリンガリズム

バイリンガリズムの言語に対する考え方は上記のようなものです。L1とL2が別の枠で囲まれていることからもわかるとおり、第一言語と第二言語が別個のものとして存在しています。
また、各言語の中に、「F1」という語彙が含まれています。
例えば、「英語」と「日本語」という言語があるのであれば、その中に英語なら「cherry blossoms」「English」「table」などの語彙、日本語なら「さくら」「日本語」「テーブル」などの語彙が含まれているという考えです。
二つの言語が一つ一つ独立しているということがこのモデルの前提になります。
コードスイッチング(二言語併用)というのも、このモデルに基づくものです。コードスイッチングというのは、あくまで別個の言語が混ざり合っているという前提のもとに考えられた概念です。
相互依存モデル

次にある考え方は、Cumminsという有名なカナダの言語学者の提示したモデルです(ご興味のある方は『Cumminsの相互依存モデル、BICSとCALPについて』をご覧ください)。
このモデルでは、第一言語と第二言語は関係し合っているというものです。根底にはcommon underlying proficiency(共通する基礎能力)というものがあって、第一言語の能力は第二言語にも転移し、その逆もしかりというものです。
なお、彼のモデルは継承語教育というディアスポラ・移民の子供の教育などにもかなり影響を与えました。
Translanguaging

さて、本題のTranslanguagingですが、それは上記のような考え方です。「L1」や「L2」という言語体系がなくなっているのにお気づきでしょうか。
Translanguagingの考え方では、個人が複数の言語を別々に持っているのではなく、それらが統合された一つの言語レパートリーとして機能していると考えます。
「さくら」「cherry blossom」「英語」「English」「table」「テーブル」も個人の中では一つの言語レパートリーとして存在しているという考え方です。それが、社会的には「英語」「日本語」などというように分けられているという理解です。
要するにtranslanguagingというのは、1つ1つの言語が独立して存在するのではなく、自分の1つの言語レパートリーの中から言葉を使うということを指します。
García and Li(2014, p. 2)では、以下のように説明しています。(翻訳は拙訳です)
[Translanguaging is] an approach to the use of language, bilingualism and the education of bilinguals that considers the language practices of bilinguals not as two autonomous language systems as has been traditionally the case, but as one linguistic repertoire with features that have been societally constructed as belonging to two separate languages.
参考文献&興味のある方は
Translanguagingについて興味のある方は以下の本を読むと理解が深まるのではと思います。
特にGarcíaはTranslanguaging研究の第一人者なので、彼女の著作にあたるといいかと思います。
トランスランゲージング教育論に着目した本ですが、最初のほうにトランスランゲージングの説明もあります。日本語で読みたい方におすすめです。
また、Translanguagingは批判もされています。それについて興味のある方は以下の記事もご覧ください(備忘録なので読みづらいと思いますが…。申し訳ありません)。
- Translanguagingの実施例・問題点・課題などをまとめたCenoz & Gorter (2017)を読みました。
- CanagarajahのTranslanguagingの理論・実践上の課題を提起した論文を読みました。
- translanguagingについてのマルチリンガルな視点を提起したMacSwanの論文(2017)を読みました。
バイリンガリズムに興味がある方は以下の記事もご覧ください。